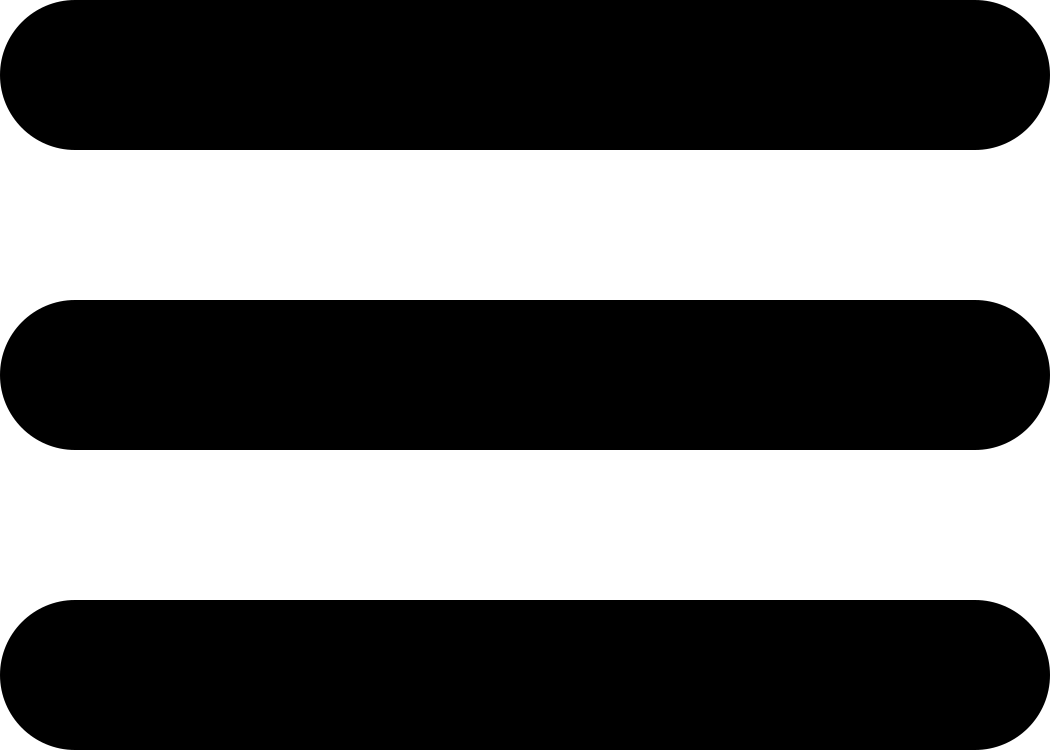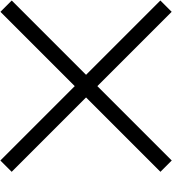『アンナチュラル』が放送されたのは、2018年の1月クール。早いもので、もうすぐ2年が経つ。しかし、視聴者の中にはいまだ本作の思い出が鮮烈に残っているのではないだろうか。「面白かった」という脳に残る感覚と、「泣いた」という心が記憶している感情。きっと本作は、この先も永く語り継がれていくだろう。
このドラマが、なぜここまでの人気を獲得したのか。アンナチュラル(不自然)な要素は何もない。「構造」「キャラクター」「ストーリー」……そしてドラマならではの「ウソ」のバランスが非常に高く、1話単位の密度=見ごたえが半端ではないのだ。
元々、医療系×感動のドラマというのは、『コード・ブルー』しかり『ブラック・ジャックによろしく』しかり、本作と共通項も多い『きらきらひかる』しかり、とても人気のジャンルだ。毎話、患者たちの生きざま(或いは死にざま)が描かれ、そこに医療従事者たちの人生がリンクし、さらに病気の原因や死の真相を探るサスペンスやミステリー要素も加わり、嗜好と感情の両方を満たしてくれる。(その分、作り手にとっては専門知識や撮影場所などハードルが高い。役者においても医療ものはセリフ覚えが相当大変だという)
その中で『アンナチュラル』は、「壮絶な生い立ちを持った主人公」「恋人の死の真相を追う孤高の天才」「語り手となる新米」「面倒見のいい班長」といった鉄板ともいえるキャラクターを生き生きと描きつつ、それぞれの“情”を丁寧につづっていく。基本的にこういった形式の作品は、エピソードごとにそれぞれのキャラクターが主軸となり、深掘りが行われていくものだが、『アンナチュラル』もその流れに従いつつ、独自の特徴がある。
それは、一貫して「正義」を描いていることだ。主人公の三澄ミコト(石原さとみ)は一家無理心中の生き残りだが、そのことによって倫理観や道徳心がゆがむことはない。「なぜ自分だけが生き残ったのか?」と悩み苦しむ姿もフォーカスはされない。ただ、彼女は「生きること」に対して独自の信念を持っており、ミコトが投げかける言葉は作品の“芯”として鋭く響く。
「無理心中なんて言うのは日本だけ。正しくはmurderer suicide。殺人と、それに伴う犯人の自殺。単なる身勝手な人殺しです」「絶望する暇があったらうまいもん食べて寝る」「未解決の事件の遺族には、終わりがない」……。彼女の言葉ににじむのは、「生きることの大切さ」と、「死んでしまった者への敬意」だ。その彼女の死生観が、恋人を何者かに殺された中堂系(井浦新)の歪な執念とぶつかり合い、物語のダイナミズムを生み出している。
この作品独自の面白さとは、「曲がっていない」ことではないだろうか。あまりに凄惨な事件を生き延びたミコトだが、彼女はその事件の陰に生きるのではなく、その事件を糧として、「自分のような思いをさせない」ことを信条とした。『アンナチュラル』は、ドラマにおける“被害者”の新たな形を構築したともいえるだろう。「死」を扱う作品ではあるが、力強い希望を描いたドラマなのだ。